読書感想|地元を生きる
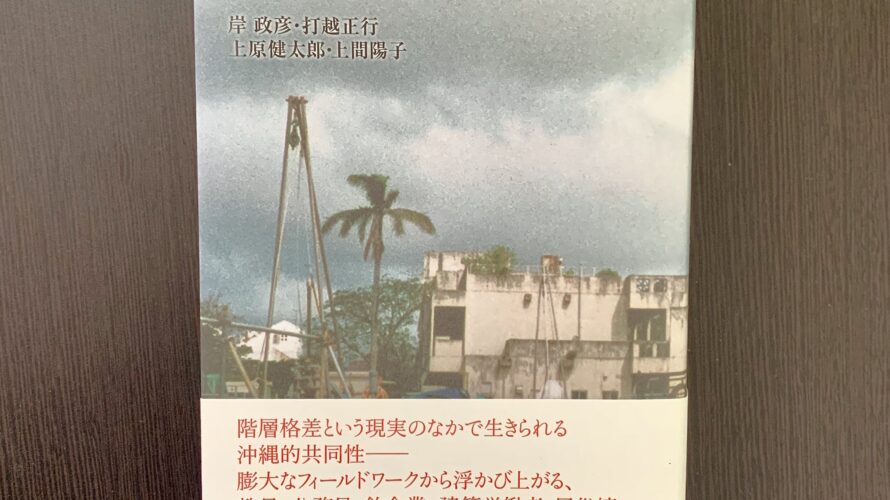
岸 政彦・打越 正行・上原 健太郎・上間 陽子(2020).地元を生きる──沖縄的共同性の社会学── ナカニシヤ出版
本書紹介 from ナカニシヤ出版
階層格差という現実のなかで生きられる沖縄的共同性──。
膨大なフィールドワークから浮かび上がる、教員、公務員、飲食業、建築労働者、風俗嬢……さまざまな人びとの「沖縄の人生」。
ここにあるのは、私たちがたまたま出会った、小さな、ささやかな断片的な記録である。しかしこの「生活の欠片たち」を通じて、私たちなりのやり方で沖縄社会を描こうと思う。……私たち日本人は、一方で「共同性の楽園」のなかでのんびりと豊かに生きる沖縄人のイメージを持ちながら、他方で同時にその頭上に戦闘機を飛ばし、貧困と基地を押し付けている。本書は、少なくともそうした沖縄イメージから離脱し、沖縄的共同体に対するロマンティックで植民地主義的なイメージが、基地や貧困とどのように結びついているかを、日本人自身が理解するための、ささやかな、ほんとうに小さな一歩でもあるのだ。――序文より
本書感想
沖縄は面積2,281km2,人口145.7万人(2020年2月2日),人口密度640人/km2の小さな島である。地縁・血縁の絆が強く,沖縄的共同体として憧れの目でみられることもある。
その内実を描いた本書は,沖縄社会の分断を描いている。狭い地域である沖縄にいる人たちの話であるはずなのに,まったく違う世界に住む人たちが描かれているように思える。いかに沖縄が一枚岩でないのかがわかる。
「ささやかな断片的な記録」とあるように,ここで描かれる沖縄は一側面でしかない。その一側面からでも,沖縄がいかに多様であるかがわかる。
何かを理解するとは,理解できないこととセットなのであろう。私たちがもつ「〇〇ってXXだよね」というイメージは,理解しているようでいて,実は理解できていないことの現れなのであろう。きっと理解に終わりはないのだと思う。だからこそ人は早急な「理解」を求めるのかもしれない。
この早急さにいかに抵抗するか。『地元を生きる』はその一つの試みだったのではないかと思う。
-
前の記事
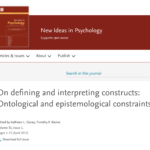
開催記録|【第2回】特集「On defining and interpreting constructs」を読む@オンライン 2020.12.13
-
次の記事
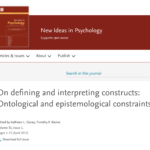
【第3回】特集「On defining and interpreting constructs」を読む@オンラインのお知らせ 2020.12.16