査読に関する戯言

先日,査読を説明する記事を書きました。
それを書いたあと,思い出したことがあったので備忘録として残しておきます。
自分が査読者になった時の自戒も込めて。
最近,査読を受けるとよく言われることがあります。
「〇〇については先行研究があると思いますので,引用してください」
もっとも実りのない指摘の一つだと思います。
自分の論文を書く上で当然のこととして,テーマに関連のある先行研究は一通り読みます。もちろん全部が読めるわけではないのですが,それなりの数を読みます。その上で論文を書き,関連のある先行研究を引用しながら論じているわけです。逆にいうと,引用していない先行研究は関連がない,あるいは,論文にとって重要ではないから引用していないわけです。
それにも関わらず,査読者が「先行研究があるから引用して」とだけ言うのは,どういう意味で言っているのか?と思ってしまいます。
「XXの点で〇〇の先行研究が不足しているから追加した方がいい」「〇〇の先行研究を引用するとXXの点で説得力が増す」など,その指摘を行う具体的な理由が書いてあれば頷けます。しかし,「研究の意義を明確にするために」という抽象的な理由での指摘は,「なぜ引用しなければいけないのか」について査読者としての説明責任を果たしていないと思います。引用する理由が抽象的なのであれば,せめて先行研究の引用の仕方に関する指摘は具体的である必要があると思います。要するに,査読者がコメントするにあたり,抽象的なコメントはただのマウンティングでしかないと個人的には思っています。
査読はピアレビュー(同僚による評価)ですが,査読者と投稿者にはどうしても権力関係が入り込んできます。業績をあげる必要のある場合は特にそうだと思います。そこに敏感であれば,コメントは丁寧で対話的になると思います。査読はボランティアで忙しいなか行なっていることは百も承知です。最近,査読を頼まれる機会が増えてきましたが,その権力関係に敏感になって,具体的で丁寧で対話的なコメントを心がけていきたいと思います。
-
前の記事

備忘録|査読についての説明 2020.05.30
-
次の記事
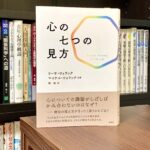
読書感想|心の七つの見方 2020.06.01